かけはしプロジェクト代表北島です🌈
NHK番組「とく6徳島」を見てくださってありがとうございました。
応援のメッセージをくださった方もありがとうございました。
私自身病気して初めて高次脳機能障害や失語症という障害を知りました。
まるで頭が幼稚園児に戻ったような感覚もしくは認知症にでもしまったかのような感覚。
当たり前にできていたことができない。
要領悪いし、文字が書けないなんて。
そんな自分と向き合う辛さ。
それをどんなに家族や支援職の方が寄り添ってくれてもなぜか満たされない気持ちがずっとあった。
「そんな言葉をかけてくれても、実際なってしまった今の辛さやどこにもぶつけられない感情なんて分からんでしょ。」
そんなひねくれた感情を押し殺しながら日々を過ごしていた。
そんな時、もし同じようにこの障害と診断された女性や子育てママと出会う機会があったのなら思いも全く違っていたと思う。
だからそんな居場所を作りたいと思った。
この居場所を大切に守りながら、社会全体にもっと認知が広がるように幅広く講演を続け、同時に母親とその子どもの支援をしていきたい。
母親って常にマルチタスク。
朝起きてご飯して子ども起こしてご飯食べさせながら洗濯して洗い物して学校の準備して服着替えさせて、、休みの日になれば朝昼晩ご飯作ってまた食べさせて洗い物してお風呂入らせて着替えさせて洗濯して干して明日の準備したり。
それを1人目の時はふつーーーにこなせた。
それが2人目では全くできなかった。
キッチンタイマー使わないと火をつけっぱなしにしてしまったり、洗濯物回してること忘れるし、レンジに入れたもの忘れてるし、まだ小さな息子のご飯食べさせながら娘の様子を見たり話を聞いてゆっくり食事をとることすらできない。
とにかく毎日がしんどかった。
それを私自身経験したからこそまずはママ支援。
そして、毎日しんどかったのは私だけじゃなくて子どもたちもそうだった(今もそうなんじゃないか)と過去を振り返ってみても、そして今もそうなんじゃないのか。
と俯瞰して考えられるようになった。
話をしても忘れて何度も聞かれる、言っても無視されてる気がする(こっちとしては、何か他のことに集中してると聞こえてないから)、夕方になると疲れていて横になってる、いきなり電源切れる(自分の中の限界をちゃんと分かってないと脳が限界を迎えて動けなくなる)、参観日や運動会などの行事ごと忘れていて来てくれない。
子どもにもきちんと母親の症状や程度、対処法を伝えておかないとお互い辛い思いをしてしまうと思う。
当事者に子どもがいる場合は、親も子もまるっと支援しないといけないって自身の経験から強く感じる。
まずは、母親の支援。
母親が先の見えない不安な気持ちや満たされない気持ちがあると余裕を持った子育てなんてできない。
今の気持ちをわかってもらえる仲間と繋がり、時には情報共有したり、年に一度のリアル交流会でイベントに参加してくれたり。
そんなきっかけで、少し前を向くきっかけになったり癒されてくれたらいいなって思う。
妊娠中、子育て中にケガや病気をして思うようにいかなくなった身体と付き合うことになった時、使える社会資源は限られてる。
運転ができなくなった人もいる。自宅から外へ出かけることにハードルを感じる人もいる。
そうなった時、一番辛いのはもちろんママやけど、その子どもたちも同じように辛いと思う。
子どもは子どもなりにどうしても友だちのお母さんと比べてしまうと思う。
友だちのお母さんと比べてうちのお母さんは、、
それを誰にも相談できずにいたりするんじゃないかな。
今ヤングケアラー支援って言葉をよく耳にするけれど、自分がこの病気をしてよく分かった。
親と子を包括的に支援する仕組みができていないからだと。
今この世にない支援を作ろうなんてこんな熱い思いだけではどうにもならん。
色んな人に関心をまず持ってもらいたいです。
障害は決して他人事ではないということ。
自分がもしその立場に立った時、どうしますか。
どんな支援が必要ですか。
今の支援だけで子育てする自信がもてますか

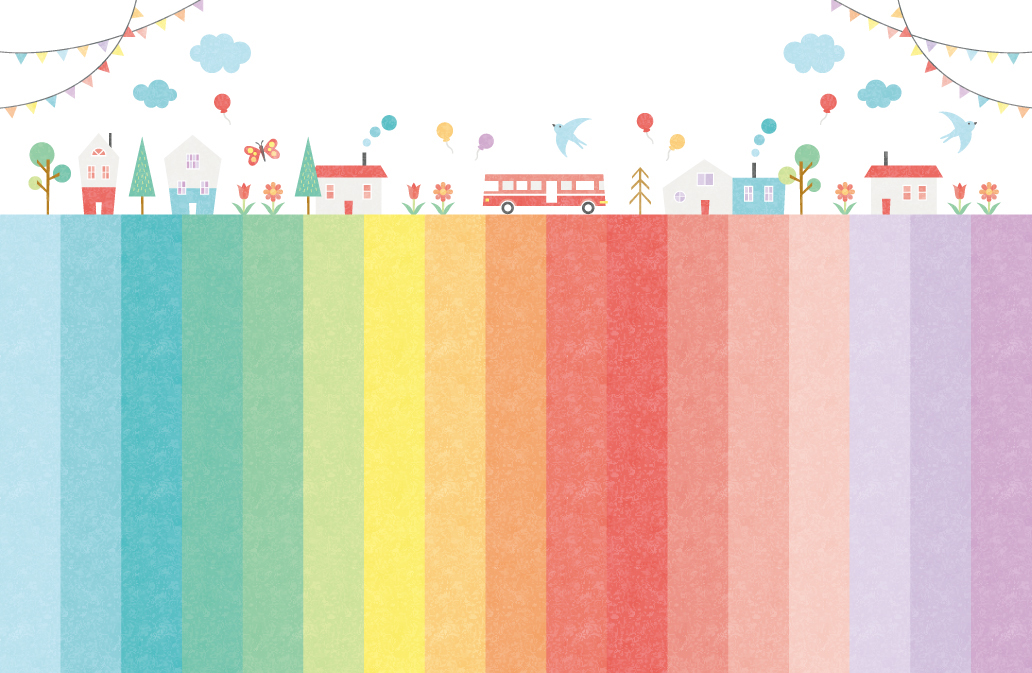





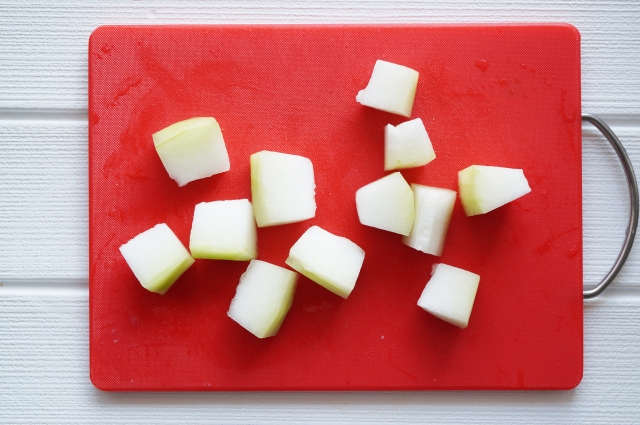

コメント